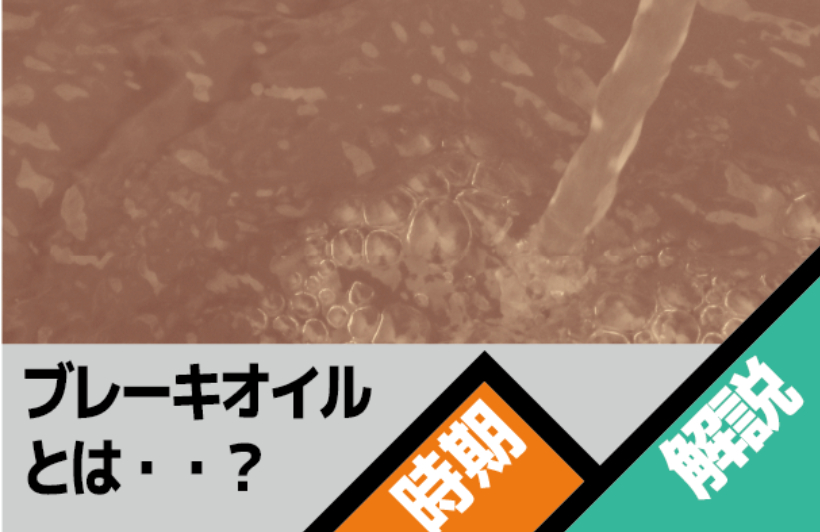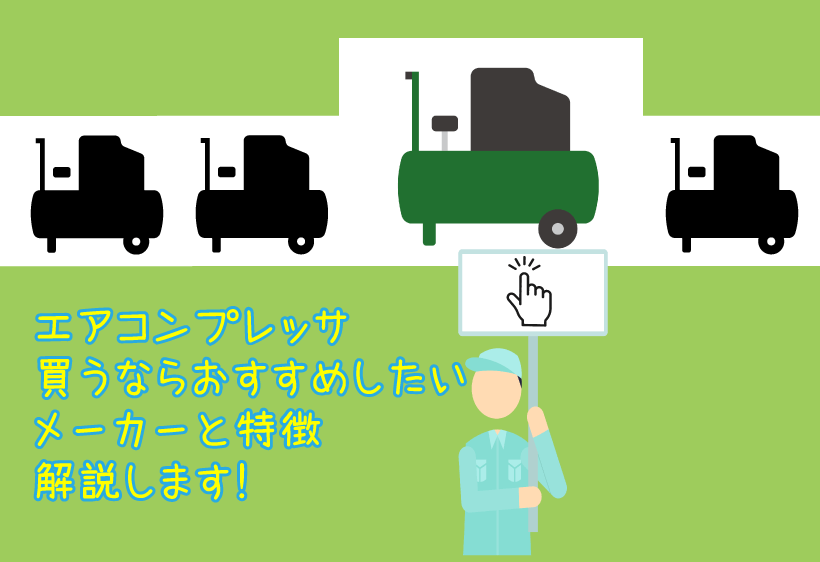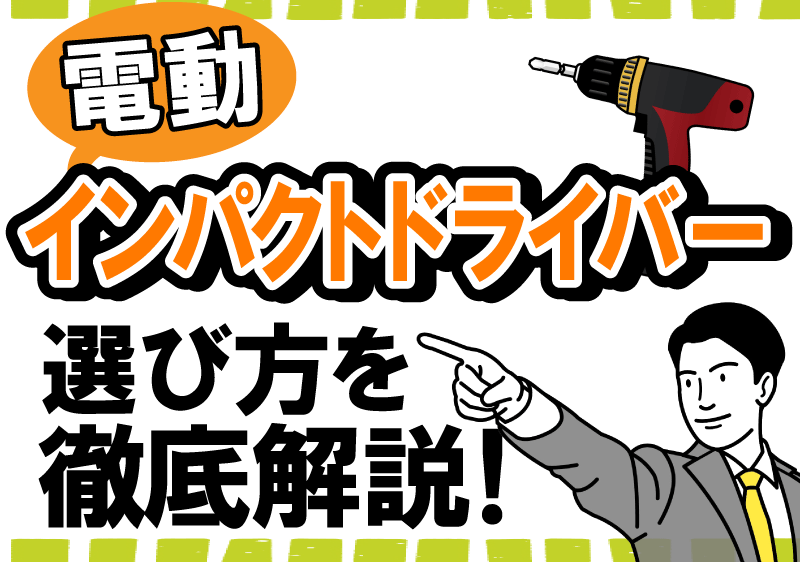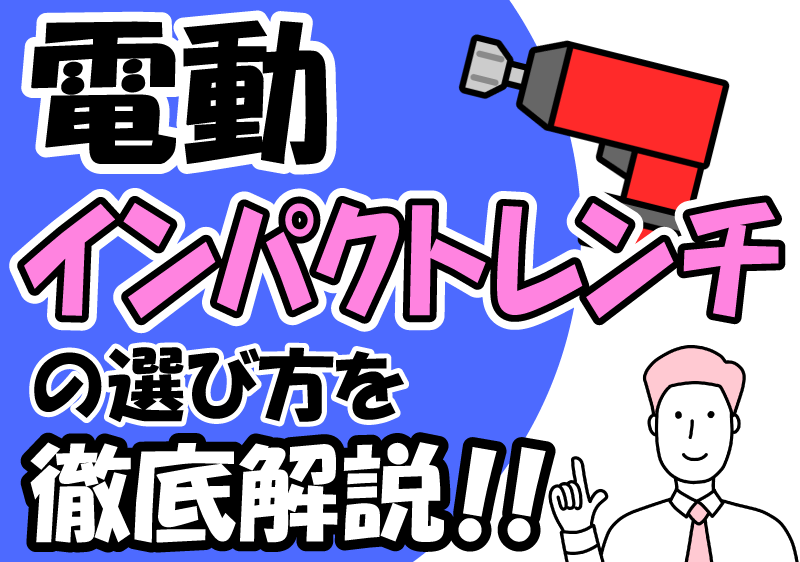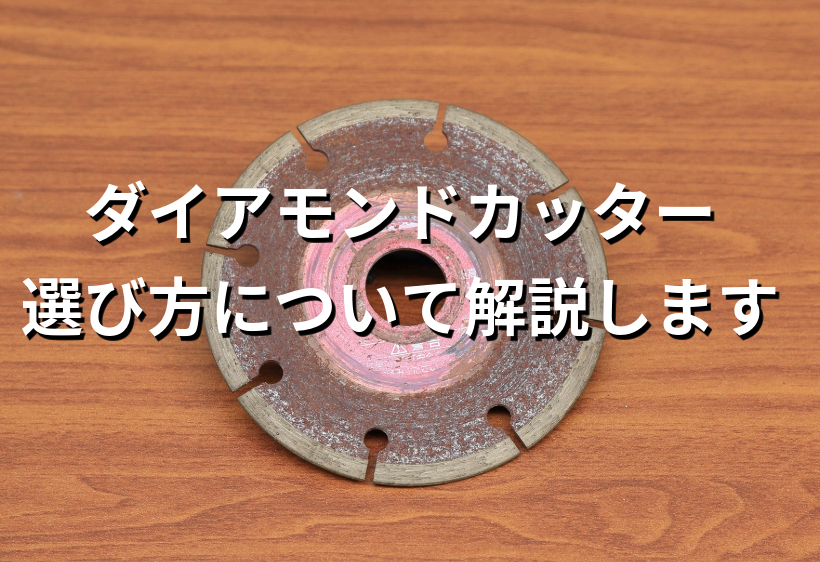スポット溶接機の選び方や種類、その他の溶接との違いについて解説します
目次

ハンズクラフト西日本最大級の工具専門リユースショップです。
ハンズクラフト【工具専門】西日本最大級の総合リユースショップです。
当店は創業20年以上、工具・家電を中心に扱うリユース専門館です。お買取りした中古品を綺麗にメンテナンスして新たな価値を吹き込み、福岡・北九州地域を中心に沖縄や山口・広島まで14店舗を展開中です。各記事は工具専門のスタッフや、工具・家電の修理専門部門が監修・執筆しています。
スポット溶接は自動車産業をはじめとする製造業のなかで、もっとも一般的な金属接合方法です。
ですが、ガス溶接やアーク溶接など、その他の溶接方法との違いについて悩む方も多いと思います。
ということで今回は、スポット溶接についての基礎知識について解説していきつつ、溶接機本体の選び方や種類などについても解説していきます。
スポット溶接について実はよく知らない…と思っている方は、ぜひ読み進めてみてください。
スポット溶接機とは

スポット溶接機は、金属同士を点状に接合する装置です。この溶接機は2枚の金属板を重ね合わせ、上下から電極で挟み込んで加圧しながら大電流を流します。
すると金属の接触部分に発生する抵抗熱が発生し、徐々に金属板同士が溶融。あとは電流を止めれば冷えて固まるので、溶接が手軽に行える仕組みです。
仕組みを以下の3ステップで見ていきましょう。
- 加圧:電極(チップ)で母材を挟み込んで加圧
- 通電:大電流を流して抵抗熱を発生させ、接合部を溶融
- 保持:溶融部を冷却させてナゲット(溶け合った部分の名称)を形成
流れにすると上記のようになりますが、実際は一瞬で点状の溶接が完了します。
スポット溶接機の大きな特徴は、作業時間が非常に短いこと。高い生産性を実現できる点にあります。
また溶接時に特別なガスやフラックスといった追加材料を必要としない(ほかの溶接では必要になることも多い)ため、経済的で環境への負荷も少ないです。
さらにアーク溶接と比較した場合、熟練した技術をあまり必要としません。初心者でも比較的扱いやすい溶接方法です。
スポット溶接機の特徴について

スポット溶接機には、ほかの溶接方法と比較して際立つ優位性があります。
まず溶接作業の効率性が非常に高く、一点あたりの溶接にかかる時間が数秒程度と短時間で済むこと。大量生産に適しています。
※DIYで利用する場合は、手軽に溶接を行えるのが大きなメリットです。
また溶接時に使用する材料が電極のみという点も見逃せません。アーク溶接だと溶接棒やシールドガスといった消耗品が必要です。
ランニングコストも抑えられますし、コスト面での優位性も高いと言えます。
さらに溶接時の熱影響が局所的であり、母材への影響が少ないことも大きな特徴です。(薄い板だと熱で曲がってしまうことも多々)
薄板の溶接でも歪みが少ないので、高品質な接合が実現できるでしょう。
操作面においても優位性が高いです。溶接条件を事前に設定しておけば、比較的かんたんに作業を行えます。
熟練工じゃなくても安定した品質の溶接が可能なのは、初心者にとって嬉しいポイントですよね。
加えて溶接時の火花や光が少なく、作業環境への負荷が小さいことも特筆すべき点です。作業者の安全性が確保しやすく、環境面での配慮もされています。
メリット
スポット溶接機のおもなメリットを見ていきましょう。まず生産性の面です。
作業の自動化が容易で、連続的な溶接作業が可能となっています。気軽な溶接だけではなく、大量生産にもおすすめです。
また1箇所あたりの溶接時間が極めて短く、作業効率が非常に高くなっています。
品質面でのメリットも大きいです。溶接部分が点状に限定されるため、熱による母材の変形が最小限。
溶接条件も一度設定すれば、安定した品質の接合が継続的に得られます。溶接後の仕上げ作業もほとんど必要ないので、製品の美観も保ちやすいです。
日々のコスト面でも、かなり導入しやすくなっています。溶接棒やシールドガスといった消耗品が不要となっており、材料費を大幅に削減可能です。
専門的な技能を必要としない点も、スキル習得費用の削減につながるでしょう。機器の維持管理も比較的容易で、ランニングコストを抑えられるはずです。
作業環境面でもメリットがあります。溶接時の煙やヒューム(金属の粒子)が少なく、作業環境が清潔です。
アーク溶接のような強い光も発生しないため、作業者の目に対する負担も少なくなっています。
作業音も比較的静かで、騒音問題も起こりにくいです。
安全性の面でも、大きなメリットがあるでしょう。火花の飛散が少なく、火災のリスクが低減されるからです。
溶接条件が機械的に制御されるので、人的ミスによる事故も起こりにくくなっています。
デメリット
スポット溶接機にも、いくつかの制約や課題があります。まず溶接可能な形状の制限です。
電極で材料を両側から挟む必要があるため、溶接できる形状や位置に制限があります。
とくに複雑な形状や入り組んだ部分の溶接が困難で、電極が届かない箇所は作業ができません。片側からしかアクセスできない場所での使用も不可能です。
材料の制約もあります。溶接可能な板厚には制限があり、厚い材料の溶接には適していません。
また異なる材質の組み合わせや、導電性の低い材料の溶接は難しいでしょう。とくにアルミニウムの溶接には、より大きな電流が必要となります。
初期導入コストが比較的高額になるのも、デメリットです。とくに大型の設備や高性能な制御機能を備えた機種は、相当な投資が必要となります。
電源設備の増強が必要になる場合もあり、付帯設備のコストも考慮する可能性がある点は押さえておきましょう。
また電極チップは使用に伴い摩耗するため、定期的な交換が必要です。電極の冷却水系統のメンテナンスも欠かせません。
こういったデメリットを押さえたうえで、適切な機器導入とメンテナンスを考えていきましょう。
スポット溶接機の種類について

スポット溶接機は、おもに定置型とポータブル型の2種類に大別されます。それぞれ特徴が異なるので、事前に押さえておいたほうが良いでしょう。
また電源形式によっても分類されるため、作業内容や環境に応じて最適な機種を選択しなくてはなりません。
各タイプの特徴と使い分けのポイントを理解し、最適な機器導入の検討に役立ててください。
定置型について
定置型スポット溶接機は、工場や大規模な製造現場で使用される「据え置き型の溶接装置」です。
大型で重量があり、一度設置するとなかなか移動できません。固定された作業場所での使用なら、定置型を使うと良いでしょう。
あまり動かせないものの溶接能力が高く、厚い材料や大きな部材の溶接が可能です。安定した電源供給により、連続的な作業にも対応できます。
溶接ヘッドを支えるアームが大きく、作業スペースが広いです。テーブルが付属しており、大型の工作物も安定して保持できます。
冷却システムも充実しているため、長時間の連続作業を行うなら定置型が良いでしょう。
用途は以下のとおりです。
- 自動車のボディ製造ライン
- 大型家電の製造工程
- 金属家具の製造
- 産業機器の組立て
出力が大きく、安定した溶接品質を維持できます。またデジタル制御により、溶接条件の細かな調整が可能。高精度な溶接作業を実現できます。
多くの機種で自動化にも対応しており、産業用ロボットとの連携も可能です。
ポータブル型について
ポータブル型スポット溶接機は、移動しながらの作業に適した小型・軽量の溶接装置です。DIYでの利用検討なら、こちらを選定される方が多いかもしれません。
コンパクトな設計で持ち運びが容易なため、現場での補修作業や小規模な製造現場での使用に適しています。
設置場所を選ばず、電源さえあればさまざまな場所で使用できる利便性が特徴です。
片手または両手で持てるサイズに設計されていて、軽量化のために冷却システムを簡略化しているものが多くあります。
アームの長さや開き幅は定置型と比べて小さめですが、狭い場所での作業に最適です。用途も見ていきましょう。
- 自動車の板金修理
- 小規模な金属加工
- メンテナンス作業
- DIYでの金属加工
ただ定置型と比べると出力は控えめで、連続作業時間にも制限があります。(薄板の溶接には十分な性能)
最新のモデルではデジタル制御により、溶接条件の調整が可能な機種も増えてきました。
電源方式の種類と違いについて
スポット溶接機の電源形式は、おもに以下3つのタイプに分類されます。
- 単相交流型
- インバータ直流型
- コンデンサ放電型
それぞれに特徴的な性質があり、用途に応じて使い分けられています。項目ごとに詳しく解説していきます。
単相交流型
もっとも一般的な電源形式で、装置がシンプルで耐久性が高め。比較的安価なのが特徴です。
鉄系材料の溶接に適しており、扱いやすさから広く普及しています。ただし熱効率の面では他の方式と比べてやや劣ってしまうでしょう。
インバータ直流型
連続的に効率よく熱供給ができ、消費電力を抑えられる特徴があります。火花(スパッタ)の発生が少なく、安定した溶接品質が得られる電源形式です。
また溶接トランスが小型軽量という利点もあります。とくにモーターのヒュージング(端子とワイヤーの接合)作業で多用されている傾向です。
コンデンサ放電型
大電流を瞬時に放電できる特徴があり、アルミニウムや銅といった導電率の高い材料の溶接に最適です。
また通電時間が極めて短いため、溶接部の圧痕が浅く、外観が良好になる特徴も。ただし電流値の制御が難しく、連続作業には向いていません。
スポット溶接機の選び方

スポット溶接機を選ぶ際は、作業内容や環境に応じて適切な機種を選定しなくてはなりません。
まず使用目的による選択を行いましょう。作業場所や使用頻度を考慮し、定置型かポータブル型かを決定します。
定期的に大量の溶接作業を行う場合は、安定した性能を発揮する定置型がおすすめです。一方で補修作業や小規模な製造なら、機動性の高いポータブル型を検討してください。
溶接する材料の種類や、厚さも重要な指標です。適切な出力を持つ機種を選ばなくてはなりません。
例えば薄い鉄板のみを扱うなら、単相交流型の小型機で十分です。
アルミニウムや特殊な金属を扱う場合は、より高性能なインバータ直流型やコンデンサ放電型を検討したほうが良いでしょう。
作業場所の電源設備も重要な検討項目です。大型の定置型を導入する場合、十分な電源容量が必要となります。
また作業スペースの広さや、溶接する製品の大きさに応じて、アームの長さや開き幅を考慮することも大切です。
最後に予算を見てみてください。初期投資額だけではなく、ランニングコストも考慮に入れる必要があります。
電極チップの交換頻度やメンテナンス費用も含めて、総合的に判断してみましょう。事前のシミュレーションが重要です。
また将来的に、作業量が増加する可能性はあるでしょうか。そういった点も見据えて、やや余裕のある性能の機種を選ぶと安心です。
スポット溶接機を買うならオススメしたい主要なメーカー

スポット溶接機を選ぶ際、メーカーから選ぶことはとても重要です。国内には長年の実績を持つ優れたメーカーが複数存在し、それぞれが特徴的な製品を展開しています。
ここではとくに注目すべき3社のメーカーについて、その特徴と主力製品をまとめました。
大同興業株式会社
大同興業株式会社は1946年設立の老舗企業で、愛知県名古屋市に本社を構える大手メーカーです。
実は大同特殊鋼グループの専門商社として、高品質な溶接機器を提供しています。
とくにTECNAシリーズのスポット溶接機は、業界内で高いランキングを獲得。信頼性の高い製品として知られています。
TECNAシリーズについてもう少しご紹介しましょう。このシリーズは高い溶接条件と加圧条件に対応しながら、従来機と比べて小型軽量化を実現しました。
ART-3664PやART-3650ECFは、幅広いスポット溶接作業にも対応可能です。
ポータブル型UPシリーズも非常におすすめですね。UP-10Dをはじめとするポータブル型溶接機は、以下の特徴を持っています。
- トランジスタによる特殊回路採用で溶接時間の調整が可能
- 小型・軽量で台車付きの高い作業性
- 自動タイマー付きで低コストとトラブル低減を実現
自動車板金やダクト、製缶、看板、板金加工と、産業分野で幅広く活用される信頼性の高い製品ばかりです。
株式会社浪速電機製作所
株式会社浪速電機製作所は、大阪府東大阪市に本社を構える溶接機器メーカーです。
エアー式スポット溶接機を主力製品として展開し、安定した加圧力による高品質な溶接を実現しています。
製品ランキングでも上位に位置し、業界内で高い評価を得ているのが特徴です。
主力製品について見ていきましょう。エアー式スポット溶接機「SU-ARシリーズ」の特徴は下記にまとめました。
- エアーシリンダーによる安定した加圧力
- デジタルタイマーによる電流値の計測が可能
- 品質管理に適した機能を搭載
エアー式スポット溶接機「SL-APシリーズ」もおすすめです。下記のような特徴があります。
- 垂直加圧式で溶接点を狙いやすい設計
- 丈夫なフレームで長期使用が可能
- フットスイッチ採用による優れた作業効率
- 自動マルチスポット溶接機
金網製造向けの自動溶接機も製造しており、ファクトリーオートメーション化に対応した製品も提供しています。(DIYというより本格的なプロ向けです)
アズワン
アズワンは研究・医療分野の専門商社として、90年の歴史を持つ企業です。
2015年からBtoB-ECサイト「AXEL(アクセル)ショップ」の運営を開始しました。研究用科学機器から工場設備まで、約600万点もの商品を取り扱っています。
※製品はAmazonでも手に入るものばかり。
同社の強みは圧倒的な商品数と、15時までの注文で即日出荷可能な高速配送システムです。
また専門スタッフによる商品選定サポートや、ヘルプデスクによる充実したカスタマーサービスも特徴的。
とくに注目すべき製品として、超小型スポット溶接装置「KTH-MWS」があります。この製品はAC100V電源で使用可能な、B5サイズのコンパクトな設計です。
重量もわずか5.4kgと軽量。初心者向けとしても、検討される方が多いのではないでしょうか。
サイリスタ位相制御方式を採用し、研究開発や生産現場での薄板、細線金属材料の溶接に適しています。
取っ手付きの持ち運びやすい設計とシンプルな操作性を備えており、DIYユーザーにも扱いやすい製品です。
まとめ
今回は、スポット溶接についての基礎知識について解説していきつつ、溶接機本体の選び方や種類などについても解説していきました。
この他にも電動工具やDIYに関する知っておきたい知識は、まだまだあります。
ぜひ、この他の関連記事も読んで参考にされてみてください。
関連記事
不要な工具は
ハンズクラフトへ
工具専門で20年
買取価格に自信があります!
大切な工具だからこそ、工具専門店にお任せください。