ホームセンターオリジナルの電動工具って使える?おすすめメーカープロモデルとの違いを解説
目次

ハンズクラフト西日本最大級の工具専門リユースショップです。
ハンズクラフト【工具専門】西日本最大級の総合リユースショップです。
当店は創業20年以上、工具・家電を中心に扱うリユース専門館です。お買取りした中古品を綺麗にメンテナンスして新たな価値を吹き込み、福岡・北九州地域を中心に沖縄や山口・広島まで14店舗を展開中です。各記事は工具専門のスタッフや、工具・家電の修理専門部門が監修・執筆しています。
ホームセンターへ行くと、よくホームセンターオリジナルブランドの電動工具を見かけますよね。
でもイメージとしては、なんだか安いしすぐ壊れそう…。そんな印象がついている方も多いのでは無いでしょうか。
今回は、ホームセンターオリジナル電動工具の強みと弱み、プロ用モデルとの違いについて解説していきます。
これから電動工具を買おうと迷っている方は、ぜひ最後まで読んで参考にされてみてください。
ホームセンターオリジナルの電動工具の強み

ホームセンターオリジナル電動工具の強みは、なんといってもその「価格設定」にあります。
プロ用モデルの半額程度で提供されながら、DIYに必要な基本性能は十分に確保。コストパフォーマンスはバツグンです。
とくに月1~2回程度の使用頻度であれば、安いからといって性能差を感じないかもしれません。実用的な選択肢として十分と言えるでしょう。
近年はホームセンターのオリジナル商品といっても、品質面で著しい向上を遂げています。
実用的な機能も標準搭載され、DIYをする上で必要な機能や付属品が充実してきました。
さらに多くのホームセンターオリジナル電動工具は、シリーズ内でバッテリーを共有できるシステムを採用しています。(今までは共用設定されていなかった)
複数の電動工具をシリーズで揃えるメリットも出てきましたし、コストを大幅に抑えられるようになっています。
一般的なDIY作業に焦点を当てた設計思想も、大きな強みです。
過剰なパワーや耐久性を想定せず、組立家具のネジ締めやウッドデッキの制作、一般的なDIY作業に最適化された性能設定。
必要最低限の機能に絞っているため、価格を抑制しながらも実用性を損なわない絶妙なバランスを実現しました。
一般ユーザーの使用頻度や用途に合わせた最適な仕様と価格バランスこそ、ホームセンターオリジナル電動工具における最大の強みと言えるでしょう。
ホームセンターオリジナルの電動工具の弱み
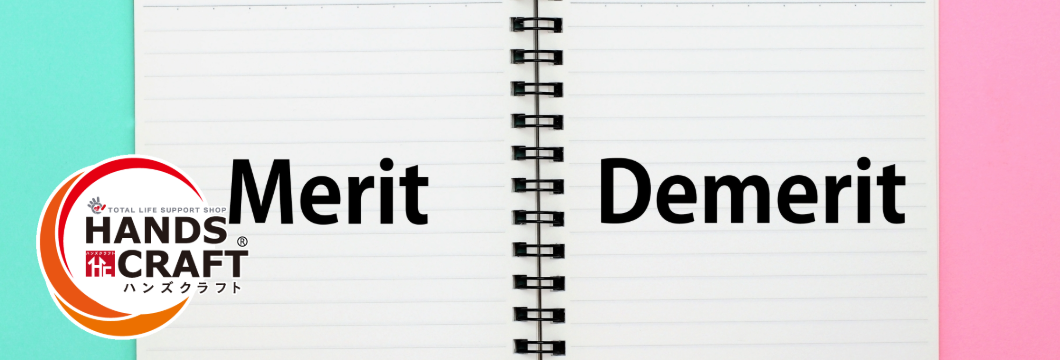
ホームセンターオリジナル電動工具の弱みは、アフターサポート体制の不安さにあります。
実は大手のホームセンターといっても、独自の修理拠点を持たないことが多いです。故障時の対応は本体交換が基本となるでしょう。
専門的な修理サービスを受けて長く使いたい、と考えるユーザーにとっては大きな不安要素となるかもしれません。
製品の継続性も大きな課題です。バッテリーや付属品の供給が突然終了するリスクもあり、モデルチェンジのタイミングも不明確。
長期的な部品供給の保証がないため、愛着を持って長く使い続けたいユーザーにとっては不安が残ります。
またプロフェッショナル向けの製品と比較すると、性能面での制約が目立ってしまうでしょう。耐久性が低く、パワーや精度も劣ります。
DIYレベルでの使用には問題ありませんが、本格的な作業や頻繁な使用(もしくはステップアップしたい方)には向いていません。
店舗スタッフの製品知識が十分ではないケースも多く見られます。適切な使用方法や製品選びについて、専門的なアドバイスを受けるのが難しいでしょう。
手頃な価格と基本性能の確保という利点がある一方で、長期的な使用や専門的なサポートという面では多くの課題を抱えています。
ただしこのような弱みは、一般的なDIYユーザーをターゲットとした製品特性から生じたものです。
悩みや不安を抱える方の場合、ステップアップのタイミングが来たとも取れるでしょう。
ホームセンターオリジナルの電動工具とプロ用モデルの違い

ホームセンターオリジナル電動工具と、プロ用モデルは一体どんな違いがあるの?と思うかもしれません。プロ用モデルは、実はDIY用と比較して明確な性能差があります。
インパクトドライバーを例にしてみましょう。プロ用は最大トルク220N・mを誇るのに対し、ホームセンターオリジナルモデルは100N・m程度。
またプロ用は精度が高く、寸分の狂いもない作業が可能です。過酷な環境での使用を想定し、耐久性を高く設計しているのも特徴と言えるでしょう。
- 雨天時の作業
- 高温多湿な環境
- 粉塵の多い現場
上記のような環境でも、安定して使用できます。一方でホームセンターオリジナルモデルは、一般的なDIY作業を想定した耐久性です。
ほかにもホームセンターオリジナルモデルは、バッテリーと充電器付きでも1万円以下で購入可能。プロ用の半額以下です。
月1~2回程度のDIY作業であれば、ホームセンターオリジナルモデルで十分な性能を発揮します。
一方でプロ用は1日8時間、週40時間程度の稼働を想定した設計です。連続作業や高負荷作業をするなら、間違いなくプロ用モデルが良いでしょう。
同じ電動工具でも、想定ユーザーが違えば注力する部分が異なります。名称のとおりプロ向けか、一般向けかの違いです。
ホームセンターオリジナルの電動工具のアフターケアは期待できる?

ホームセンターオリジナル電動工具のアフターケアは、正直なところ限定的という印象があります。
筆者は以前、2年ほど愛用していたホームセンターのオリジナル電動ドライバーでトラブルが発生しました。
バッテリーの充電が全く効かなくなり、使用不可。問い合わせた結果、直接店舗へ行くことになりました。
しかし期待していた修理対応は叶わず、「申し訳ありませんが、修理ではなく本体交換での対応となります」と告げられています。
幸い保証期間内だったので、新品との交換で対応してもらえました。もし保証期間を過ぎていれば、新たに購入するしかありません。
また店舗のスタッフに詳しい故障の原因を尋ねても、技術的な説明を受けられませんでした。(初期不良ロットという扱いで交換を受けていますが、詳細は一切不明)
「メーカー製品のような専門的な修理施設を持っていないため、細かな故障診断や部品交換などの対応は難しい」とのことです。
確かに価格の安さを考えれば致し方ない部分もありますが、愛着のある道具だけに少し寂しい気持ちになりますよね。
上記の経験から、ホームセンターオリジナル電動工具を購入する際は、アフターケアの限界をあらかじめ理解しておく必要性を強く感じました。
保証期間内であれば交換対応が可能なものの、保証が過ぎたら実質的にサポートを期待することは難しいでしょう。
価格の安さと引き換えに、長期的なケアや専門的な修理の可能性を諦める必要があります。
とはいえ月に1~2回程度のDIY作業であれば、依然としてホームセンターオリジナル電動工具は魅力的な選択肢です。
購入時には保証内容をしっかりと確認し、故障時の対応を事前に理解しておくことが重要だと実感しました。
DIY用途ならホームセンターオリジナルの電動工具とプロ用モデルのどっちがおすすめ?

DIYでの一般的な使用であれば、ホームセンターオリジナル電動工具で十分な性能を発揮します。オリジナルブランドを選択して良いでしょう。
月1~2回程度の使用頻度なら、プロ用との価格差ほど性能を実感する場面は少ないはずです。
近年はオリジナルブランドでも品質が著しく向上しており、DIYに必要な機能や付属品が十分に備わっています。
価格はプロ用モデルの半額程度でありながら、スピード調節機能やバッテリーを共用できる電動工具を多種ラインナップ。複数の工具もそろえやすい利点があります。
ただし予算に余裕がある場合、プロ用モデルを選択する価値は十分にあるでしょう。
- 精度の高い作業が必要な場合
- 長時間の連続使用を想定している場合
上記の場合、プロ用モデルの性能差が活きてきます。プロ用モデルの最大の利点は、その耐久性と安定性です。
高い耐久性による長期使用の実現、安定した精度の維持、優れた防水・防塵性能、品質面での優位性は明確と言えるでしょう。
さらに確実なアフターサポート体制も大きな魅力です。予算に余裕があるなら、最初からプロ用モデルを選んでも良いかもしれません。
プロ用工具が必要になる場面について
具体的にプロ用工具が必要な場面について、より詳しく掘り下げていきましょう。精度の高い作業が求められる場合、プロ用モデルの選択が望ましい場面が多く存在します。
例えば寸分の狂いも許されない建具の取り付けや、高精度な加工が必要な家具製作。このような場面では、プロ用モデルの精度が重要な役割を果たします。
木工作品の製作は細かな調整や正確な加工が必要となるため、プロ用モデルの性能差が作品の質に直接影響を与えることも多いです。
ほかにも一日8時間、週40時間程度の使用を想定している場合は、プロ用モデルが必須でしょう。
※建設現場での作業や、工務店での日常的な使用が該当。
また週末だけのDIYであっても一日中続けて使用する場合や、定期的に大規模な作業を行う場合もプロ用モデル検討が強く推奨されます。
連続使用での信頼性や耐久性は、作業の効率と安全性に直結するためです。
ほかにも過酷な環境での使用が予想される場合、プロ用モデルを選択したほうが良いかもしれません。
- 雨天での屋外作業や高温多湿な環境
- 粉塵の多い現場での作業
- 狭所での作業
通常以上の耐久性が求められる環境下では、プロ用モデルの堅牢性が真価を発揮します。一般的なDIY用工具だと、すぐ故障してしまう可能性が高いです。
上記のように作業の頻度や精度、環境を総合的に判断し、プロ用モデルの必要性を検討してみてください。
単に趣味のDIYであっても、要求される品質が高い場合はプロ用モデル検討の価値があります。
初期投資が高くて…と考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。
長期的な視点で見た場合、初期投資は高くても結果的に安く済む場合があります。プロ用工具はなかなか頑強ですので、一般使用ではなかなか壊れません。
ホームセンターオリジナルの電動工具を買うならオススメしたい主要なメーカーと製品特徴

ホームセンターオリジナル電動工具は、近年コストパフォーマンスだけではなく性能の向上も著しいです。
具体的に購入を検討する際、どの会社の電動工具を選べばいいか迷うこともあるでしょう。
ここではコメリとカインズ、コーナンの3社に絞って特徴をご紹介します。
コメリの「B-Share」シリーズ
コメリのB-Shareシリーズは、DIY向けに開発された充実のラインナップを誇ります。
ラインナップは以下の全5種類が用意されており、DIYに必要な基本的な工具が揃っている構成です。
- インパクトドライバー
- ドライバードリル
- ブロワ
- マルチツール
- レシプロソー
最大の特徴はバッテリーと充電器付きで、どの商品も1万円以下という手頃な価格設定です。
性能面ではインパクトドライバーなら最大トルク100N・mを発揮するため、この価格帯でこのスペックならDIY作業に十分な性能を備えています。
10.8Vのバッテリーシステムを採用し、シリーズ内で共通して使用できる設計。バッテリー容量は2.0Ahで、充電時間は約45分と実用的です。
とくにDIY初心者や、お手頃な電動工具を探している方に最適な製品ラインナップと言えるでしょう。
かんたんなリメイクから本格的な家の改修作業まで、幅広いDIY作業に対応できる設計なのは非常に魅力的。
近くにコメリがあるなら、B-Shareシリーズを検討してみても良いですね。
コストパフォーマンスの高さと使いやすさを重視した、DIY愛好家向けの実用的な電動工具シリーズとなっています。
カインズの「Kumimoku」シリーズ
カインズは「DIYer100万人プロジェクト」の一環として、DIY初心者向けに「Kumimoku」シリーズを展開しています。
このシリーズは工具を「しまわない工具」として位置づけ、安心して使える品質と使いやすい機能を重視。インテリアとしても馴染むデザイン性に着目しました。
Kumimokuシリーズの電動工具は14.4Vバッテリーシステムを採用し、DIY作業に十分なパワーを確保しています。
e-cycleシリーズなら1つのバッテリーで、電動工具から園芸用品まで使用可能。初心者でも扱いやすいよう、グリップの形状や素材にもこだわりが見られます。
価格設定は、プロ用工具メーカー製品の半額以下です。例えば3.6Vミニドライバーを見ると、ドリルビットのロック機構を備え、実用的な性能を実現しました。
基本的な木工作業には十分な性能を発揮し、2,480円と価格を大幅に抑えながらも必要な機能は確保されています。
KumimokuシリーズはDIY初心者や入門者、インテリア性を重視する層、そしてコストパフォーマンスを重視するユーザーがメインターゲットです。
手軽にDIYを始めたい人にとって、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた魅力的な選択肢となっています。
コーナンの「LIFELEX」シリーズ
LIFELEXシリーズは10.8Vのバッテリーシステムを採用しており、同ブランドの10.8V電動工具と共用可能な設計となっています。
インパクトドライバーの場合、バッテリー容量は1.5Ah。本体重量はバッテリー装着時に約1.04kgと、ガンタイプの中ではかなり軽量な設計です。
トリガーでのスピード微調整は行いやすい設計となっていますが、ボタン操作でのスピード調節機能は搭載されていません。
ハンドルは持ちやすく設計されており、長時間の作業でも疲れにくい特徴があります。
作業時の騒音レベルは約71dBと、一般的な電動工具と同程度。
ただしビスが木材に入っていくスピードはやや遅めで、ヘッドを押さえて力をかけなければ安定しにくい傾向があります。
コーナンのLIFELEXシリーズはDIY向けの入門機として設計されており、コストパフォーマンスを重視した製品です。
基本的な機能は備えつつも、サポート機能は必要最小限に。価格を抑えた設計となっています。
LIFELEXシリーズはDIY初心者や、軽作業向けに開発された実用的な電動工具シリーズです。
とくに軽量な設計は、DIY作業での使いやすさを重視。コーナンがお近くにあるなら、ぜひLIFELEXシリーズを検討してみると良いでしょう。
まとめ
今回は、ホームセンターオリジナル電動工具の強みと弱み、プロ用モデルとの違いについて解説していきました。
この他にも電動工具やDIYに関する知っておきたい知識は、まだまだあります。
ぜひ、この他の関連記事も読んで参考にされてみてください。
関連記事
不要な工具は
ハンズクラフトへ
工具専門で20年
買取価格に自信があります!
大切な工具だからこそ、工具専門店にお任せください。













